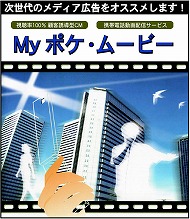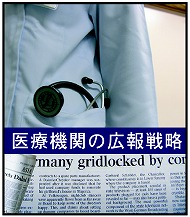広告規制緩和と医療機関の広報戦略
医療広告をめぐる制限
従来の医療広告は、安全性と社会性を確保した質の高さを求める趣旨から、「事実や客観的情報」として認められる個別事項に限り広告が可能でした。しかし一方で、以下のような問題が生じてきました。● 医療提供側と患者側の持つ情報量の差が大きい
● 意識変化や情報インフラの発達で患者の情報ニーズに適応しなくなった
そこで、広告規制を見直して、患者が医療機関を選択するための尺度(必要な情報)が検討され、2007年4月に改正医療法により広告可能事項が改められました。
広告内容に関する厳格さの緩和
主な改正点は、検査・手術・治療などについて、わかりやすい表現の使用、その説明を加えた広告、また薬事法の承認を受けている医療機器の広告、自由診療の広告などが可能になりました。例えば、これまでは「人工腎臓」「血液透析」といった広告しかできなかったものが、「人工透析」というわかりやすい表現の使用や、自由診療のインプラント治療を行う歯科医院が、「インプラント治療(自由診療:1本約○○万円程度)」と広告できるようになりました。
さらに、ドクターの略歴に出身校や学位の表記が認められ、患者の平均待ち時間、病院の施設写真、最新医療機器の有無など、患者が医療機関を選ぶ際の情報量や質が向上しました。
変わる医院・病院を取り巻く環境
現在、医院・診療所経営は、診療報酬の引き下げ、競争相手となる医院・診療所進出による患者獲得競争の激化など様々な問題により、非常に厳しいと言われています。さらに、2011年を目指したレセプションの完全オンライン化や電子カルテの導入促進により、医療の効率化も求められています。今、ドクターに望まれているのは、地域に密着した「かかりつけ医」そして、「専門性の高さ」です。これこそが、厳しい医療環境を乗り切るカギと言えます。しかし、「かかりつけ医」として患者に指名されるためにも、「専門性の高さ」をアピールするにしても、有効な媒体やマーケテイング調査、ノウハウと経験をもつ第三者の確かなサポートが必要となってきます。
さらに、広告の規制緩和により、これからは広告の有無や内容で、患者数に差がでてくることが考えられます。患者獲得競争が厳しくなる医療業界において、"患者から選ばれる病医院"として勝ち残るためには、医療広告に関する情報をしっかりと把握し、正確にわかりやすく伝える広告を行うことが重要です。
広告を組み合わせることが相乗効果を生む
一概に"広告"といっても、その種類はさまざまです。主に信頼できる媒体として、開業時に大多数の病医院で行われている「新聞広告」が挙げられます。新聞広告のメリットとしては、新聞の詳報性と記録性を兼ね備えた紙面展開で、より多くの情報を読者に伝えることができる点にあります。
しかし、一方で、持続性・継続性という効果は期待できません。長期間、地域で診療を行っていくためには、患者をはじめとした地域の方々にアピールし続けなければなりません。
そこで、新聞等の印刷媒体と次世代の広告媒体といわれる携帯動画CM(Myポケ・ムービー)を組み合わせて、効率よく・タイミングよく接触機会を多くすることで、大きな相乗効果が得られるのです。
弊社では、病医院の専門性や地域、診療科目を考慮して、それぞれの病医院に適した紙媒体をプレゼンします。さらに他院との差別化が図るために、紙媒体にQRコードを掲載し、「診療方針」、「患者や地域への想い」、「良質」、「誠実」、「安全」、「清潔」等のイメージをデザインしたオリジナル携帯動画CMを配信。見た方に好印象を持って頂き、「1度、受診してみよう」と喚起させ、効率的かつ長期間にわたり、"患者から選ばれる医院づくり"をサポートして参ります。